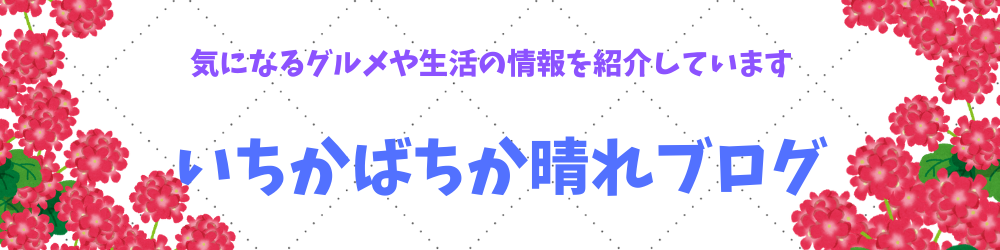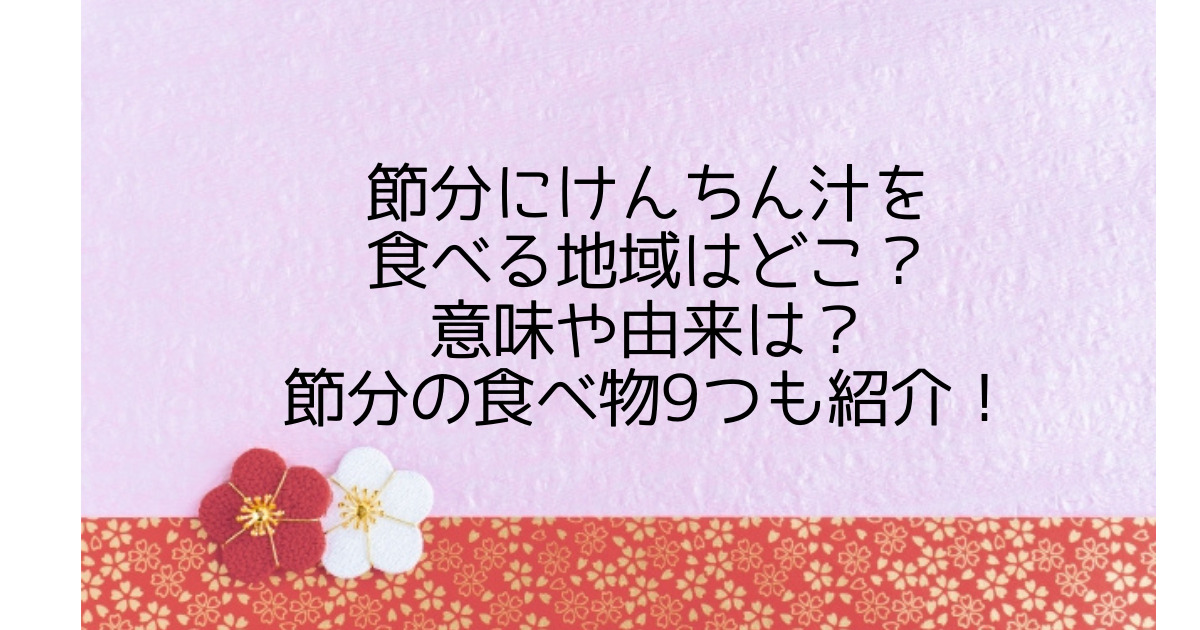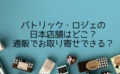節分と言えば豆まきや恵方巻をたべたりするのが主流ですが、節分にけんちん汁を食べるという地域もあります。
聞きなれない人には不思議な風習ですよね。
そこでけんちん汁を食べる地域やなぜけんちん汁を食べるのかを調べてみました。
さらに節分にはけんちん汁以外にどんな食べ物が食べられているのかも一緒にご紹介します!
節分にけんちん汁を食べる地域はどこ?
節分にけんちん汁を食べる地域は「関東の一部」と言われています。
節分というと恵方巻のイメージを持つ人が多いと思いますが、恵方巻はもともと関西圏で食べられていたものです。
恵方巻は江戸時代から明治時代にかけて大阪の花街で節分をお祝いしたり、商売繁盛を祈って食べられていたそうです。
節分にけんちん汁を食べる意味は?
関東の一部では七福神の恵比寿様を祀って商売繁盛を願う「えびす講」 や「初午(はつうま)」 などの冬の行事の時に、体を温めるために食べられていました。
寒い時期の行事に暖かいけんちん汁食べていたことから、節分にもけんちん汁を食べるようになったと考えられています。
節分だからけんちん汁を食べるのではなく、冬の行事にけんちん汁を食べていたということですね。
けんちん汁発祥の由来は?
けんちん汁発祥の由来には2つの説があると言われています。
鎌倉にある建長寺の建長汁から
まず1つ目は、鎌倉にある有名なお寺「建長寺」からという説。
建長寺を開設した蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)という僧が、野菜の皮やヘタを無駄にしないようにと余りものの野菜や崩れたお豆腐を使って作った建長寺汁。
この「建長汁」がなまって「けんちん汁」になったと言われています。
中国の普茶料理「巻繊」(けんちん) から
もう1つは中国の精進料理である普茶料理(ふちゃりょうり)の巻繊(けんちん)という料理が変化して「けんちん汁」と言われるようになったという説です。
巻繊(けんちん)は、せん切りにした大根、椎茸、きくらげ、ごぼうや崩した豆腐を炒めて湯葉や油揚げで巻き、揚げたり蒸してからダシ汁をかけた料理で、この巻繊(けんちん) の中に入る野菜や豆腐で作った醤油仕立ての汁物を「けんちん汁」と呼んだそうです。
千切りは本来「繊切り」と書くのが正しい書き方です。 巻繊(けんちん)は字の通り千切りにした野菜を巻いている料理で、現在でいう春巻きのようなものではないかと考えられています。
豚汁とけんちん汁の違いは?
けんちん汁と豚汁(とんじる・ぶたじる)はどちらも大根、ごぼう、人参、里芋、こんにゃく、豆腐などをゴマ油で炒めて、出汁で煮込んだ汁物です。
具材が似ているので間違われやすいですが「けんちん汁は豚肉が入っていない醤油仕立ての汁物」、「豚汁は豚肉が入っている味噌仕立ての汁物」です。
けんちん汁は精進料理だったので肉や魚を使わず、ダシも昆布や椎茸から取ります。けんちん汁を味噌で作る人もいますが、元々は醤油ベースのすまし汁になります。
節分のけんちん汁レシピ
けんちん汁の基本的なレシピをご紹介します
【材料】(2人前)
- 大根…100g
- 里芋…3個(100g)
- にんじん…1/3本(50g)
- ごぼう…1/2本(50g)
- こんにゃく…100g
- 木綿豆腐…1/3丁(100g)
- 水…700ml
- 醤油…大さじ2
- 和風顆粒出汁…小さじ2
- ゴマ油…大さじ1
【作り方】
- 大根、にんじん、ごぼうの皮をむいて食べやすい大きさに乱切りにし、ごぼうは水にさらしてアクを抜きます。里芋は皮をむいて半月切りにします。
- 豆腐、こんにゃくは人一口大に切ります。
- 中火に熱した鍋にごま油を熱して1とこんにゃくを入れ、全体にごま油が馴染むまで炒めます。
- 3に水、醤油、顆粒出汁を入れ沸騰したらアクを取り、10分~15分程、具材がやわらかくなるまで煮ます。
- 木綿豆腐を入れひと煮たちさせたら完成です。

お好みで油揚げやネギ、しいたけを入れても美味しくなりますよ。
節分の食べ物の意味や由来を9つご紹介!
節分の目的は「邪気を追い払うこと」
そして節分は各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日で、「季節の変わり目」や「季節を分ける」ことを意味しています。
節分は本来年4回ありますが、現在では2月の節分(立春の前日)が有名ですね。
そして旧暦では立春の頃が一年の始めとされており、立春を新年とすると「立春の前日」に当たる節分が大晦日にあたります。
大晦日だとわかると節分の食べ物にも納得なものがたくさんありますよ!。
そば
「節分そば」は縁起物として昔は全国的に食べられていました。
今では節分に蕎麦を食べる地域が減りましたが、長野県や島根県では食べられています。どちらも蕎麦で有名な地域ですね。
ソバは細長い食べ物なので「細く長く」から健康長寿や家門繁栄の願いとして。
さらに麺類の中でもソバは切れやすいので厄を立ち切る、厄落としなど縁起の良い食べ物という意味があります。
旧暦では節分が大晦日にあたるので、江戸時代の後期には大晦日でなく節分に食べるそばを「年越しそば」と呼んでいたそうです。
そのため節分のことを「年越し」という地方が今でもあります。
恵方巻き
七福神にちなんだ縁起物の具材を7つ巻き込んだ太巻きを、その年の縁起が最も良い方向(恵方)に向かって願い事をしながら黙って食べるというもの。
黙って食べるのは、話すことで福が逃げてしまうと言われているからです。
恵方巻には福を巻き込むという意味もあり定番の具材は、穴子(うなぎ)、えび、かんぴょう、しいたけ、きゅうり、だし巻き卵、桜でんぶです。
最近ではツナやカニが入ったものなど色々な具材の恵方巻が売られていますね。
大豆(福豆)
節分には「鬼は外、福は内」と唱えながら豆をまきますが、昔は病気や災害をもたらすのは鬼の仕業と考えられていました。
そこで豆を投げて鬼(魔物)や邪気を追い払い、幸運を呼び込む儀式として節分に豆まきをしていました。
豆を使う理由には「魔を滅する」ことから魔目(まめ)=豆とする理由があると言われています。
また昔の中国の医学書に「大豆は鬼毒を殺し痛みを止める」と書かれていたのが理由ともされています。そして鬼を「射る」から「炒る」の語呂合わせで、豆まきには炒り豆を使うという説もあります。
炒り大豆は「福豆」と呼ばれ、まいた豆を年の数だけ食べることで「福を取り込んで、健康に過ごせますように」という願いが込められています。
北海道や東北地方、鹿児島、宮崎県など地域によっては大豆ではなく落花生をまく場所もあります。
福茶
本来は新年に初めて汲んだ水(初水)で入れるお茶を「福茶」といいます。
節分も新年を迎えるための行事なので、1年の邪気を祓い無病息災を願う縁起物として福豆を入れたお茶を飲むようになりました。
年齢を重ねると福豆を年齢の数だけ食べるのは大変になってくるので、そんな時は福豆を入れた福茶がおすすめです。
福茶の作り方は福豆にお茶を注ぐだけで作ることが出来るのでとても簡単です。
もっと縁起を担ぎたい場合は豆まきに使った豆を三粒、塩昆布、梅干しを入れてお湯または熱いお茶を注ぎます。これでさらに縁起の良い福茶の完成です。
豆には「まめまめしく働く」、昆布は「よろこぶ」、梅干しは松竹梅などの「縁起のいい花の1つ」という意味からきていています。
けんちん汁
寒い季節の行事に体を温める食べ物として節分にもけんちん汁が食べられていました。
けんちん汁に縁起担ぎなどの意味はとくにありませんので、その家の風習や好みで食べるという感じですね。
いわし
鬼はイワシの匂いと焼いた煙を嫌がると言われていたことから、家に鬼を寄せ付けないように節分にイワシを食べて邪気を払うという意味合いがあります。
また鬼は柊のとがった葉も嫌がることから、焼いたイワシの頭に柊の枝を指した柊鰯(ひいらぎいわし)を家の玄関や門に飾り、鬼が家の中に入ってこないように魔除けにしていました。
柊鰯 (ひいらぎいわし) のことを西日本では焼嗅(やいかがし)、やっかがし、やいくさし、やきさし、とも言います。
柊鰯 (ひいらぎいわし) の風習は平安時代からあったそうで、お正月に家の門に飾ったしめ縄に柊の枝とボラの頭を刺していたことが土佐日記に書かれています。
麦飯
麦飯は縁起物で厄除けとして麦飯といわしを一緒に食べるという風習があり、そのような話が落語にも出てきます。
節分に麦飯を食べる地域は西日本に多いようです。
むかし麦飯を炊くときには麦を加熱して1晩置いた「よまし麦」と言われるものと、米を混ぜて炊飯していました。
その 「よまし麦」 という言葉から「よう回す」→「世の中がよく回るように」という語呂合わせに変わり、縁起の良い食べ物として節分に麦飯を食べるようにりました。
くじら
節分にくじらを食べるのは山口県の風習で、「節目に大きなものを食べると良い」と考えられています。
節分という節目に大きなくじらを食べることで大きな幸せを願ったり、大きく元気な子に育ってほしいという願いが込められています。
こんにゃく
食物繊維が豊富なこんにゃくは 「砂おろし」・「胃のほうき」と言われ、体内の掃除をして悪い物を取り除くとされています。
節分の節目に「こんにゃく」を食べることで体の毒素を出し、体を清めるという意味合いがあります。
まとめ
節分にけんちん汁を食べるのは関東の一部で、節分だから食べられていたということではなく寒い季節の行事に食べられていたなごりです。
そして由来は建長寺の建長汁がなまったもの、中国の普茶料理の巻繊(けんちん)からという2つの説があります。
けんちん汁には縁起を担ぐような意味合いはありませんが、栄養もとれて体も温まるので冬の行事にはぴったりな汁物ですね。
節分はけんちん汁以外にも色々な食べ物があるので、参考にしてぜひ取り入れてみて下さいね!